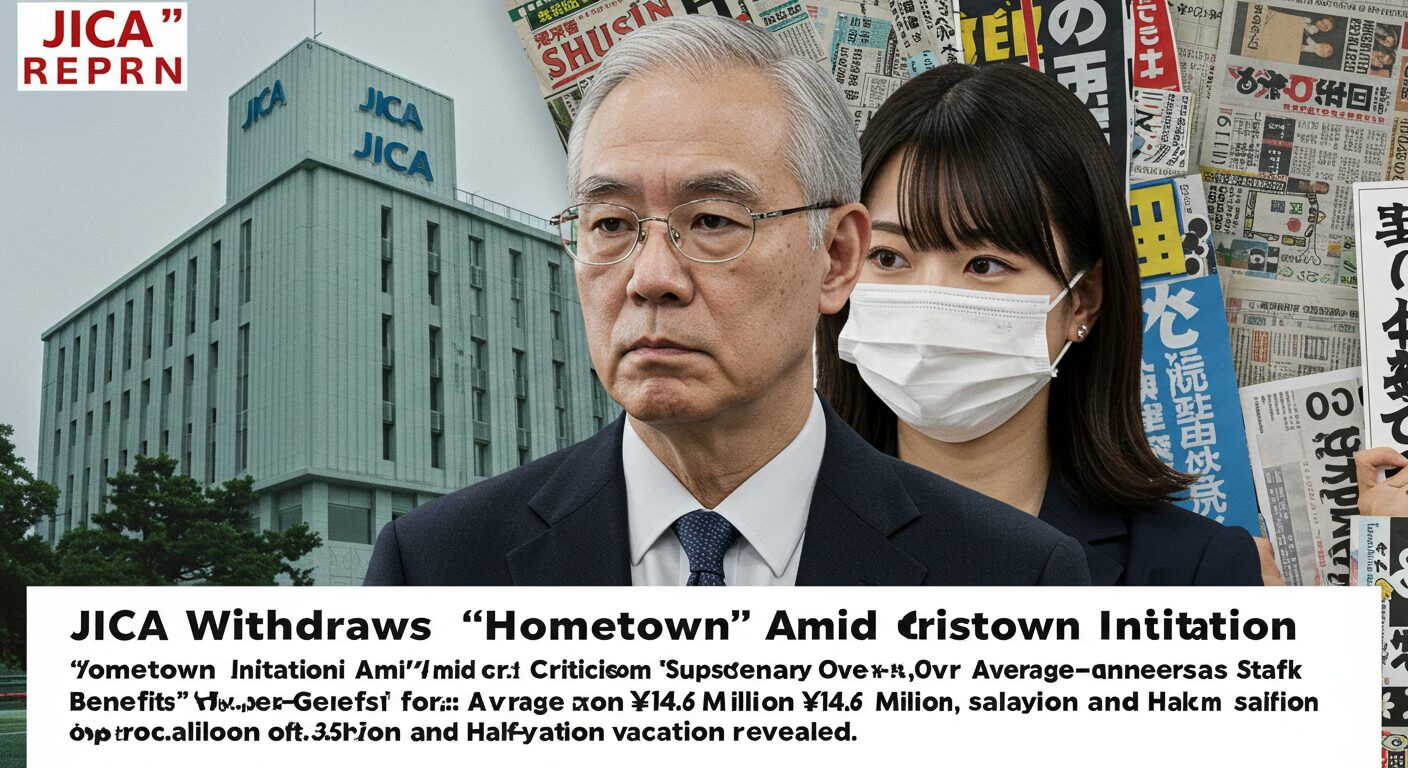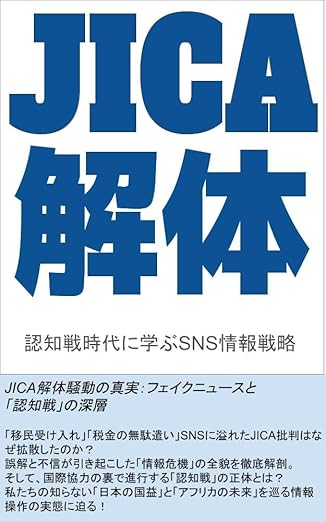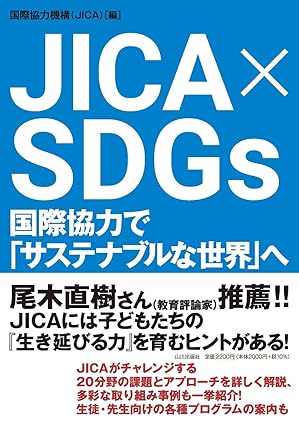独立行政法人・国際協力機構(JICA)が推進していた「アフリカ・ホームタウン交流事業」が、国内外で大きな波紋を呼んだ末に撤回された。背景には「移民促進」との誤解が拡散したことに加え、同機構の在外職員が享受している厚遇が改めて注目を集め、国民の不信感を強めることとなった。
「ホームタウン構想」とは何だったのか
JICAは8月下旬、日本政府主催の「アフリカ開発会議(TICAD)」の場で、千葉県木更津市や山形県長井市など4自治体を「アフリカ諸国のホームタウン」に認定すると発表した。これは自治体とアフリカの特定地域を結び付け、人的・文化的交流を深めることを目的とするものだった。
しかし、発表直後から波紋が広がる。対象国の一つであるナイジェリア政府は、自国の公式HP上で「日本政府が特別なビザを発給する」と記載。さらにタンザニアの現地メディアが「日本が長井市をタンザニアに捧げる」と報じるなど、誤解を招く情報が相次いで流布された。
SNS上では「黒人の町が日本に誕生する」「仲間よ、日本に行こう」といった投稿が急増。移民の受け入れが既成事実化するかのような空気が広がり、瞬く間に日本国内へ拡散した。
抗議殺到と撤回の決断
国内世論は急速に反発に傾いた。対象となった自治体には連日、抗議の電話やメールが殺到し、通常業務が滞るほどの影響が出た。JICA本部前にはデモも発生し、現場は混乱を極めた。
JICA側は「特別ビザの発給や移民促進は一切ない」と繰り返し説明し、火消しに努めた。しかし不安や怒りに包まれた世論を抑えるには至らず、最終的に「アフリカ・ホームタウン」交流事業は9月25日付で白紙撤回されるに至った。
「ホームタウン」という名称自体が移民受け入れを想起させる点も、批判の的となった。国民感情とのズレを露呈したJICAの姿勢に対しては、「国民の不安に無頓着」「海外に対して安易な約束をした」といった厳しい指摘が相次いでいる。
在外職員の「常識外れの待遇」
今回の騒動を機に、改めて注目されたのがJICA在外職員の待遇である。
2024年度の試算によれば、在外職員の平均年収は1464万円。しかも海外勤務のため所得税の納付は免除されている。さらに国ごとに異なるが、アフリカ勤務の場合は月20万円から50万円程度の住居費が公費から支給されているという。
現地で活動する関係者によれば、こうした手厚い補助に加え、職員の中には「年の半分が休暇」と豪語する者も存在するという。実際に出張を兼ねた旅行や、任期終了前に「思い出作りの観光旅行」を行う事例も報告されており、「国際協力」という建前とはかけ離れた実態が浮かび上がる。
謎の「高地健康管理休暇制度」
特に批判が強まっているのが、「高地健康管理休暇制度」と呼ばれる仕組みだ。標高2000メートル以上の地域に1カ月以上滞在する在外職員を対象に、健康維持を目的とした第三国への休暇旅行が年数回認められている。この旅費も公費で賄われており、現地の日本人社会からは「税金で家族旅行ができる制度」と揶揄されている。
制度の根拠について問われた際、在外公館が「科学的な証拠はない」と回答した例も報じられており、合理性を欠く制度として疑問の声が広がっている。JICA側は「高地に長期滞在すると酸素不足で血液中の赤血球が増え、循環障害を来す場合がある」と説明しているが、説得力に欠けるとの指摘は根強い。
国民の視線と今後の課題
独立行政法人であるJICAは、外務省所管の下で国際協力を推進している。開発途上国のインフラ支援や技術協力などを担う重要な組織であることは間違いない。しかし、その活動が「厚遇の温床」「利権構造の一部」と国民に映れば、信頼を失うのも当然だろう。
すでにJICAの運営には、天下りポストの確保や海外における非効率な「箱物事業」といった問題も指摘されている。今回の炎上は単なる広報上のミスではなく、組織体質そのものへの不信を浮き彫りにした格好だ。
血税を原資とする以上、国民に説明責任を果たし、制度の見直しや透明性の確保を急ぐ必要がある。国際協力の名の下で続いてきた慣行が、果たして時代の要請に即しているのか。今回の「ホームタウン構想」騒動は、JICAのあり方を根本から問い直す契機となるだろう。模の使命”が隠されているのかもしれません。

 |  |