人気YouTuber・Bappa Shota氏の動画に、「中国当局による仕込みではないか」との指摘が浮上している。
指摘の発信源は、篠原常一郎氏によるYouTube配信だ。篠原氏は、自身の動画内で「YouTuberのDrew Binsky氏が同じ人物・同じ舞台・同じ構成で動画を撮っている」として、その背後に“企画パッケージ化”された情報操作の可能性があると警鐘を鳴らした。
果たして、この主張にはどれほどの根拠があるのか。
今回は動画の内容・登場人物・背景構造を整理しつつ、その信憑性と論理性を検証する。
広がる「香港コフィンハウス」企画の連鎖
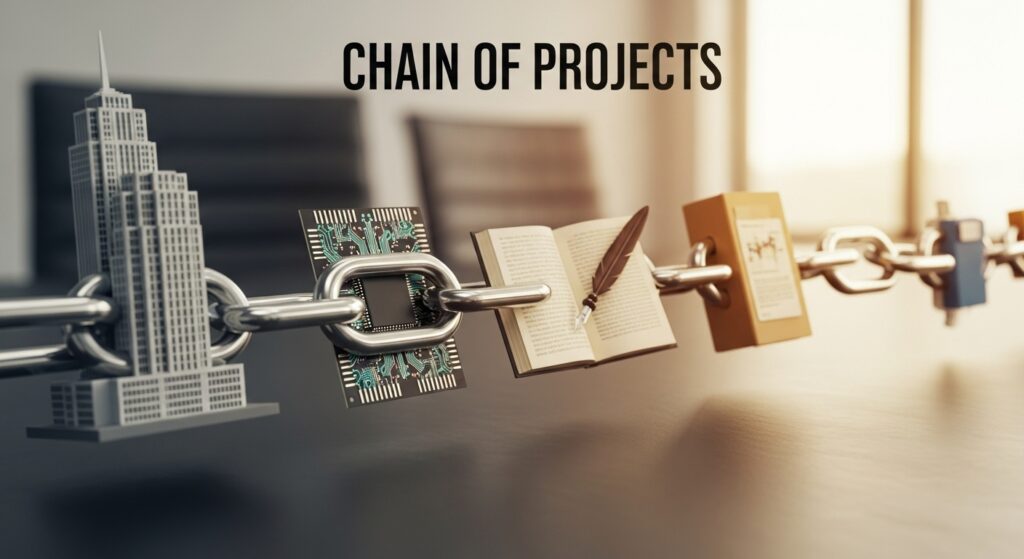
問題の中心にあるのは、「香港の棺桶住宅」「ケージハウス」と呼ばれる極端に狭い居住空間を取材した動画群だ。
このテーマは2010年代以降、香港の住宅問題を象徴するモチーフとして多くのメディアが取り上げてきた。
近年では、
- Drew Binsky
- Bald and Bankrupt
- Bappa Shota(バッパ翔太)
など、世界各国の旅系YouTuberが同様の映像を公開しており、特に2023〜2024年にかけて類似の構成が急増した。
動画はいずれも、「狭すぎる生活空間」「貧困層の現実」「それでも明るく生きる香港人」といったストーリーで展開される。
しかし篠原氏は、これらの映像に“あまりに多くの共通点”が見られる点を問題視した。
篠原氏の主張:「同じ人」「同じ部屋」「同じ構図」

篠原氏によれば、Bappa Shota氏と他のYouTuber(ドリブリンスキー、Binskyなど)の映像には、
以下のような共通項が見られるという。
- 登場人物の重複
同一の老人・女性が複数のチャンネルに登場している可能性。 - セット・小物の一致
部屋のレイアウト、洗濯物の位置、服の掛け方などがほぼ同じ。 - ナレーション構成の共通性
動画の導入・問題提示・感動的な結末といった流れが一致。
さらに篠原氏は、登場する「ソーシャルワーカー」や「案内役」とされる人物に注目。
その中の一人、“ジェライシャン”という女性が、香港の支援団体「香港コミュニティ組織協会」と関係しており、同団体は中国本土からの新移民支援を掲げていると指摘した。
彼はこの点をもって、動画の裏に「社会政策的な意図」や「当局の宣伝的構造」があると見立てた。
確かに“似ている”、だが「当局仕込み」と断定できるか?
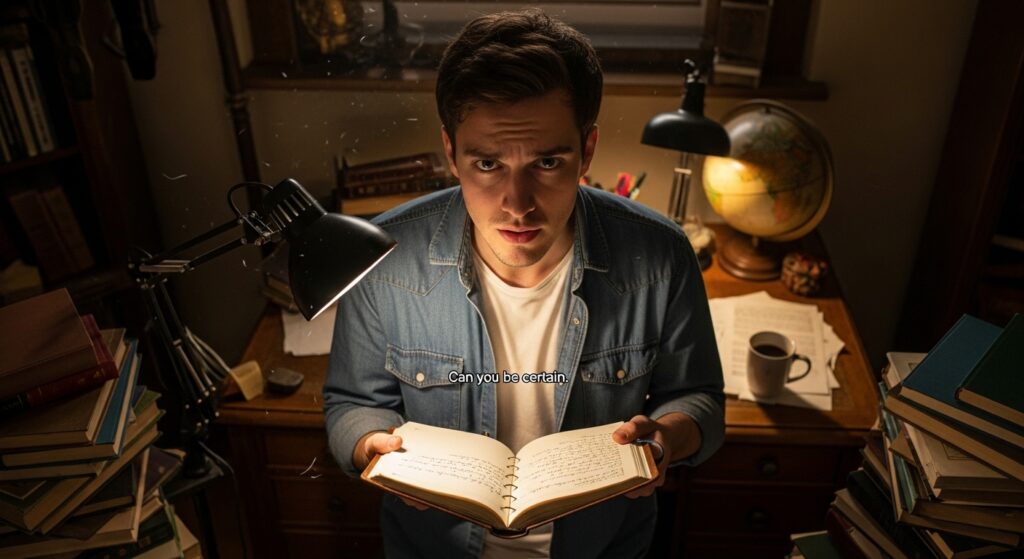
映像を確認すると、確かに同じ地域・似た構図の取材が多数存在する。
狭いアパートの撮影アングル、登場する人物像、撮影協力者などが似通っており、「同じ部屋では?」と思える場面もある。
しかし、ここで注意すべきは「似ている」ことと「同じである」ことの違いだ。
香港のケージハウスは構造が画一的で、同じ地区ではほぼ同様の部屋が並んでいる。
取材を仲介する現地NGOや通訳業者が同一である可能性もあり、複数のクリエイターが同じ被写体を紹介されるケースは十分あり得る。
つまり、“同一の構造・人物・背景”が存在したとしても、
それが「中国当局の仕込みによるもの」とは直ちに言えない。
また、篠原氏が引用する「2021年の中国共産党中央による大外宣方針(外国向け情報発信の強化)」も、実際に存在する政策文書ではあるが、そこにYouTuberを動員する具体的計画は明記されていない。
ゆえに、政策レベルと個別動画を直接結びつけるには、証拠の飛躍がある。
この主張が示す“情報環境の不安”

今回の騒動で浮かび上がったのは、映像の“似ている”という事実以上に、
視聴者が情報の真偽をどう判断するかという問題だ。
SNS時代、私たちは映像を「現実の証拠」として受け入れやすい。
しかし映像もまた、撮影・編集・構成という“意図の産物”である。
篠原氏の警鐘は、メディアリテラシーの観点から見れば一定の意味を持つ。
一方で、その主張自体もまた“解釈”であり、検証を伴わない断定は新たな誤解を生むリスクがある。
疑うことと、断定することのあいだで
確かに、Bappa Shota氏の動画には他のクリエイターと共通する構図が多く見られる。
だが、「中国当局が仕込みを行った」という断定には、現時点で客観的な裏づけがない。
映像の重複は、政治的な仕掛けよりも、YouTube取材の仕組みや現地コーディネートの構造によるものと考える方が自然だろう。
ただし、この件は「国境を越えた情報操作」という観点から見れば、注視すべき現象でもある。
今後、各制作者や関係団体への聞き取り、映像メタデータの検証などが進めば、より明確な構図が見えてくるはずだ。

 |  |

