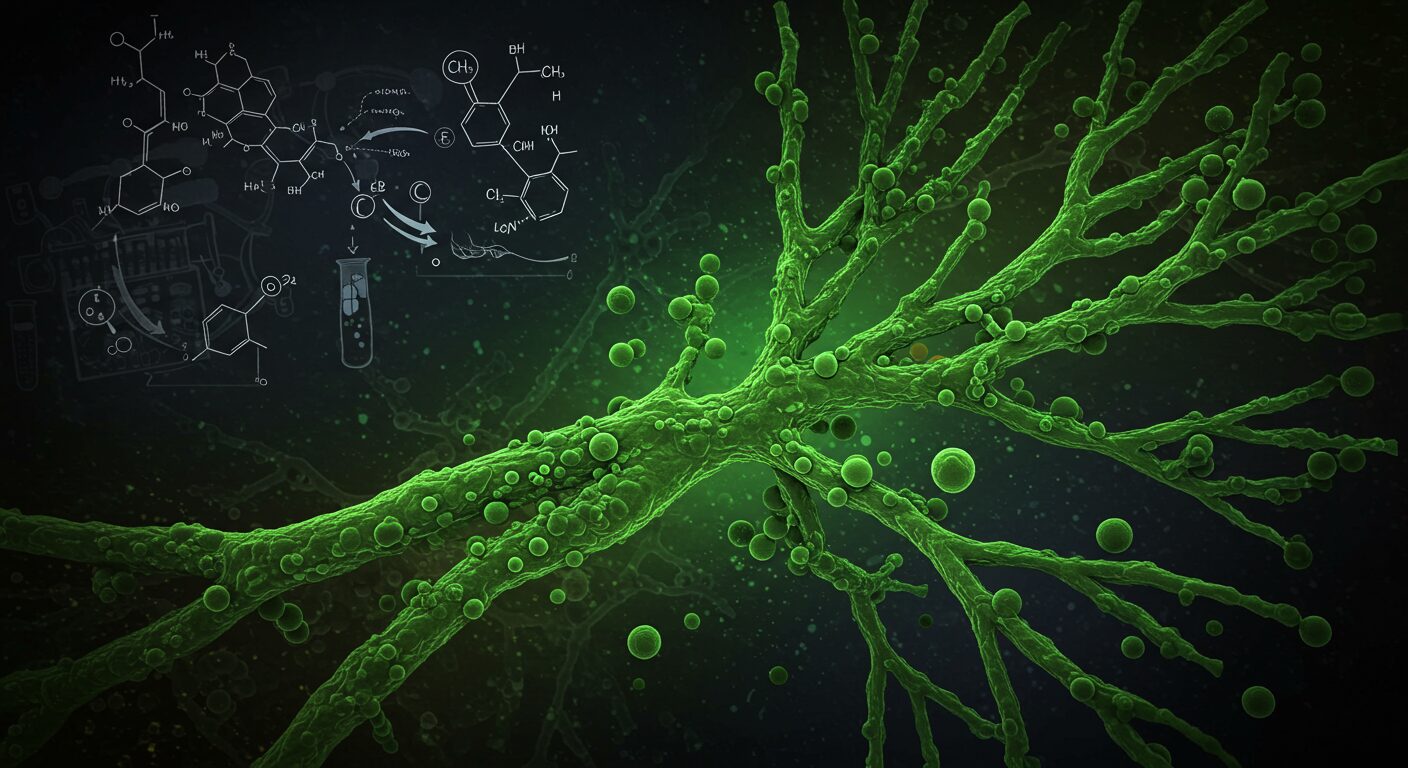1920年代、エジプト・ルクソール近郊でツタンカーメン王の墓が発掘された際、関わった考古学者のうち数人が、発掘から数週間~数カ月のうちに原因不明の病気で亡くなりました。その不可解な死は、当時「ファラオの呪い」として新聞をにぎわせました。しかし、医学の進歩とともに明らかになったのは、ある微生物の存在です。
死の原因として浮かび上がったのは「アスペルギルス・フラバス(Aspergillus flavus)」という有毒カビでした。このカビは土の中や古い建物、長年密閉された空間に潜み、胞子として空中に漂います。吸い込むことで肺に感染症を引き起こすことが知られており、特に免疫が弱っている人にとっては命に関わることもあります。
その後も、このカビが関係していると思われる死亡例が世界各地で報告されています。1970年代には、ポーランドで王族の墓を発掘していた科学者12人のうち10人が、調査後まもなく命を落としました。墓の内部からは、やはりアスペルギルス・フラバスが検出されたのです。この黄色い胞子を放つカビは、いまや“ファラオの呪いの正体”として認識されています。
毒から薬へ:カビから生まれたがん治療薬
そんな“死のカビ”が、一転してがんを倒す武器として脚光を浴びることになりました。ペンシルベニア大学の研究チームは、アスペルギルス・フラバスから取り出した化学物質に注目し、「リップス(RiPPs)」と呼ばれる特殊なペプチド分子を発見しました。このペプチドは細胞内のタンパク質工場であるリボソームによって作られ、化学的に手を加えることで性質を変えることができます。
チームはこのペプチドを人工的に改変し、白血病のがん細胞に対する働きを実験しました。その結果、4種類の新しい分子のうち2つが強い抗がん作用を示し、これらは「アスペリジマイシン(asperigimycins)」と名付けられました。
さらに、アスペリジマイシンに脂質を結合させた変異体を作成し、薬の効果を高めることに成功しました。この新しい化合物は、白血病の標準治療薬である「シタラビン」や「ダウノルビシン」と同等の効果を示しました。
研究者たちは、アスペリジマイシンががん細胞の細胞分裂を止める力があることも発見しました。この薬は、がん細胞の分裂装置である微小管の形成を妨げ、がんの増殖を食い止める作用があります。特筆すべきは、この薬が白血病細胞に対してだけ強く働き、他の正常細胞や細菌にはほとんど影響を与えない点です。
現在、研究チームは動物実験への移行を準備しており、将来的には人間への臨床試験を目指しています。かつて「呪い」として恐れられてきた古代のカビが、最先端の医療を切り開く手がかりになるという、科学によるドラマが現実のものとなりつつあります。

 |  |