アメリカ在住の「警察官ゆりのアメリカ生活」ゆり氏が、カリフォルニア州で成立した新法「AB495法案(Family Preparedness Plan Act of 2025)」について警鐘を鳴らす動画を公開した。
動画は約25分にわたり、冒頭の雑談や日常話を交えつつも、法案の仕組みや潜在的な危険性を非常に丁寧に解説している。ゆり氏は、「これは単なる法律改正ではなく、子供の安全を脅かす可能性がある制度だ」と強調し、視聴者に法案の詳細を注意深く確認するよう呼びかけた。
コメント欄には「知っていてよかった」「家族に知らせるべき」という反響が相次ぎ、SNS上でも法案の危険性に関する議論が活発になっている。
ゆり氏は動画内で、単なる条文の紹介に留まらず、過去の類似法制や他州での実例、専門家の意見も紹介することで、視聴者に法案の潜在的リスクを具体的に理解させようとしている。この点からも、AB495法案が表向きの目的とは異なるリスクを抱えていることが伺える。
「紙1枚で他人が子供を引き取れる」という現実
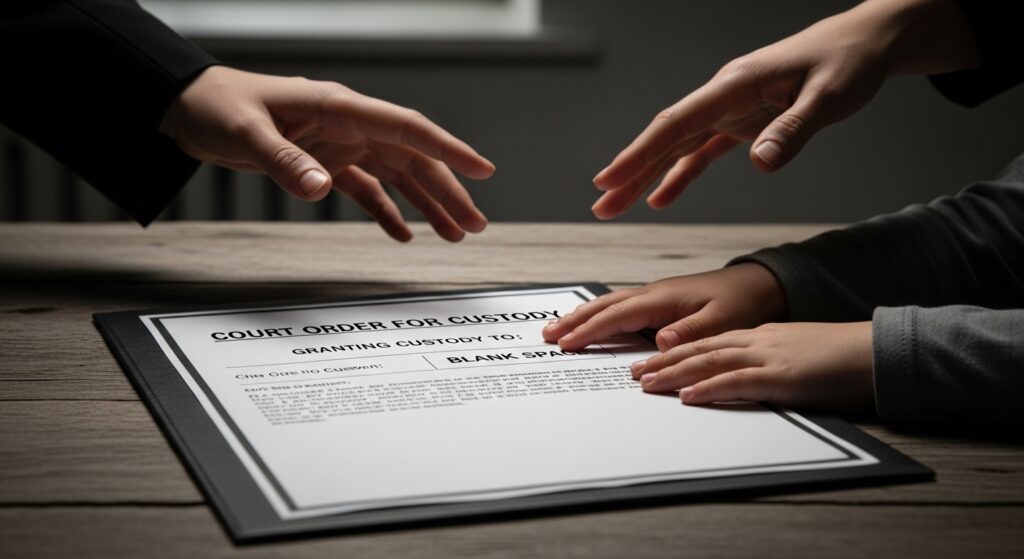
AB495法案の最も問題視されているポイントは、親以外の第三者が子供を“ケアギバー(養育者)”として引き取る権利を持つ点だ。
ゆり氏によれば、引き取りにはオンラインで取得・印刷できる宣誓書(Affidavit)と署名のみが必要であり、親の事前承認や裁判所の審査は不要という。この宣誓書には形式上「親が指定した人物」と記載されているが、法文上は提出者の正当性や資格を厳密に確認する条項は存在せず、誰でも提出可能な余地が残されている。
専門家は「この制度では、子供の引き取りを正当化する『形式だけの書類』が存在することになる」と指摘。善意に基づく行為であっても、現場での濫用や誤解が生じるリスクは高いという。例えば、知らない第三者や一時的に知り合った人物が書類を提出した場合、親権者が気付かぬうちに子供が連れ出される可能性も否定できない。
裁判所も関与する“共同保護者”の曖昧な扱い

さらに深刻なのは、この宣誓書が裁判所で「親権に近い効力」を持つ可能性がある点だ。
動画の中でゆり氏は、裁判所が宣誓書を受理すると、第三者が実質的に親権に近い権利を得ることになると解説している。通常、親権や保護者指定の判断は、裁判所や社会福祉機関が慎重に行う必要があるが、AB495法案はこのプロセスを大幅に簡略化している。
ゆり氏は次のように警告する。「形式上は親が指名した人ですが、法的な監査がなくても裁判所はこれを認める構造になっています。子供の福祉を守るためのチェック機能が完全に欠落しているため、誤った判断や不正利用が起こるリスクが高いです。」
専門家も同意しており、「制度の趣旨は災害時や緊急時の一時的なケアの柔軟化ですが、条文の不備により恒常的な親権の移譲として悪用される可能性があります」と述べている。
「身元確認禁止」条項の危険性
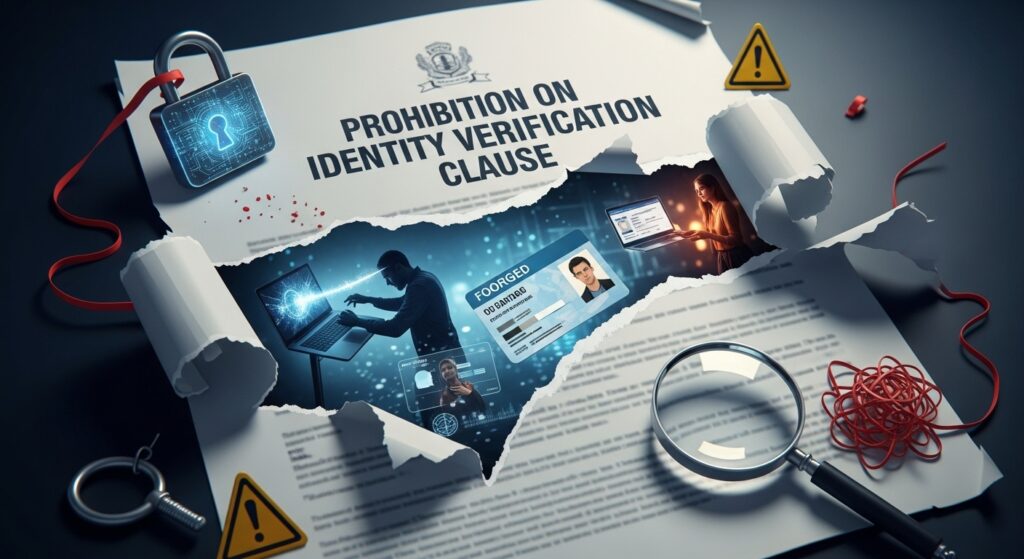
AB495法案には、学校やデイケア職員が児童や保護者の身元や移民ステータスを確認・記録することを禁止する規定も含まれている。
ゆり氏はこの条項を「不法滞在者や犯罪者でも、身元確認なしで子供を扱える余地を生む危険な規定」と説明。さらに、ライセンスを持たない施設でも運営可能な条項が含まれており、デイケアや一時的なケア施設の安全性が損なわれる恐れがあるという。
例えば、保育園や学童で発生した軽微な事故やトラブルも、身元確認ができなければ責任追及が困難になり、法的な保護も制限される。この点で、AB495法案は表向きの「家庭準備制度」を超えて、家族や地域社会に潜在的リスクを生じさせるとゆり氏は警告している。
支持派の主張と反論

AB495法案を支持する側は、「災害時や緊急事態における柔軟な子供のケア体制の整備」を目的としていると説明する。法案は、自然災害や緊急避難時に家族が迅速に対応できるよう、地域社会や親族が協力する仕組みとして正当化されている。
しかしゆり氏は、「現行の条文では制度の濫用や不正利用が可能であり、善意に名を借りた犯罪行為の温床になりうる」と反論している。実際、法文には「善意で行った行為なら免責される」という文言があり、“善意”の解釈次第で誰でも子供を引き取れる余地が残されている。この点が、法案を表向きの目的と異なるリスクを孕む制度としている最大の理由だ。
ゆり氏の結論:家族を守るために知るべき現実

動画の締めくくりでは、AB495法案が「家族の名を借りた制度改変」であることを強調。ゆり氏は「この法案を知らなければ、子供の安全を自ら守ることはできない」と呼びかけている。
さらに、親や市民に向けて次のような具体的アドバイスも示した。
- 法文を直接読んで理解する
- 地元の議員や自治体に意見を届ける
- 家族や地域社会で情報を共有し、緊急時の対応を事前に話し合う
ゆり氏のチャンネルは、他州への影響や、災害時・日常生活における具体的な対応策も紹介予定であり、AB495法案が単なる州内法改正にとどまらず、家庭や地域社会全体の安全保障にも関わる問題であることを示唆している。

 |  |

