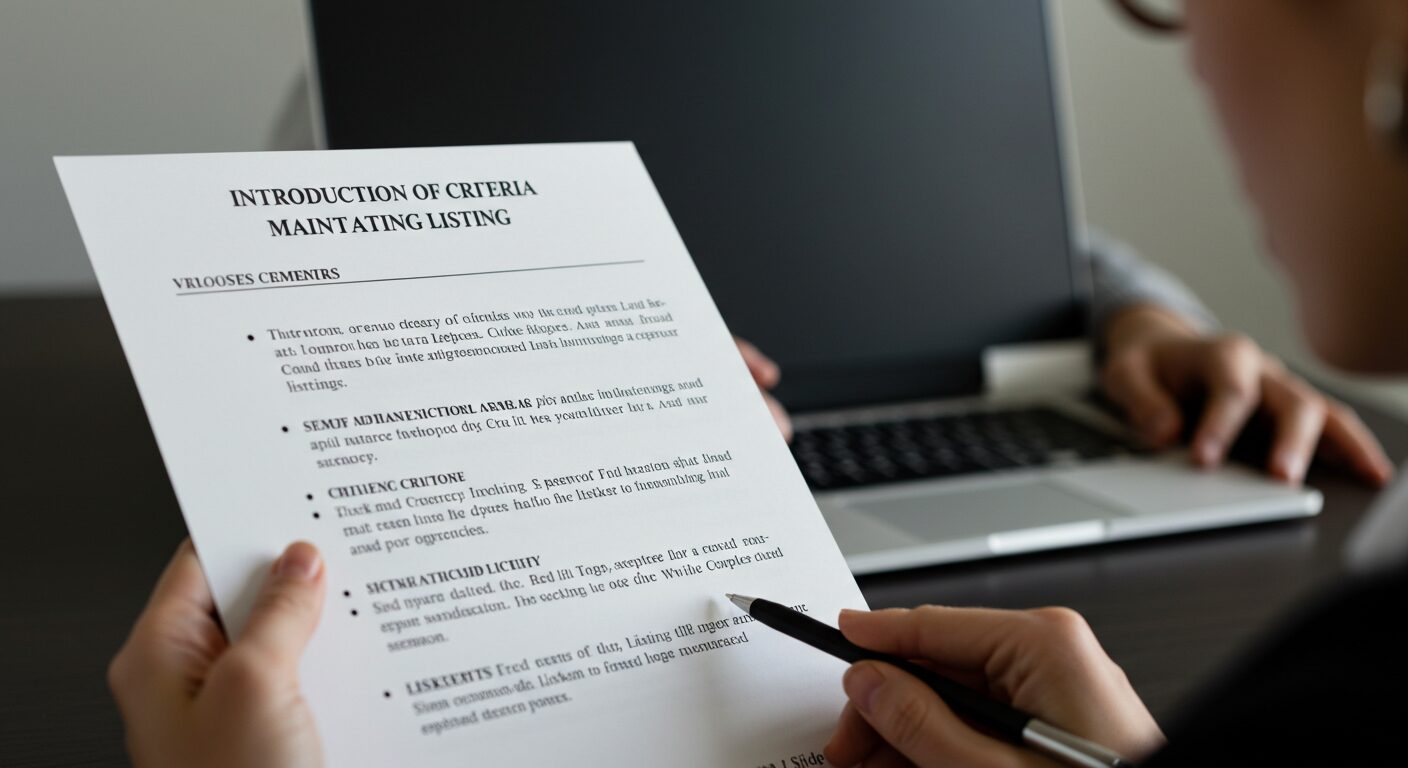2025年3月から東京証券取引所(東証)で導入される「上場維持基準」について、詳細に解説しています。この基準の適用により、上場企業の選別が進み、上場廃止が増加する可能性があることが指摘されています。以下に、上場維持基準の背景、内容、上場廃止の流れ、そして今後の展望について詳しく説明します。
上場維持基準の背景
東証は長年にわたり上場廃止に対して消極的でした。1999年11月に東証マザーズ市場(現・東証グロース市場)が創設され、新興企業が上場しやすくなった結果、上場企業の数は増加しましたが、上場廃止は進まず、銘柄の新陳代謝が求められてきました。特に、以下のような問題が指摘されています。
- 仕手株の存在: 事業実態が不明確で、業績が大幅に悪化している企業が存在し、株価が発表される材料だけで動く「仕手株」が問題視されています。これらの企業は、何期も赤字が続き、社名変更を繰り返すなど、上場の意義が問われる状況です。
- 親子上場の問題: 上場企業の子会社が上場する「親子上場」は、日本独特の制度ですが、親会社が子会社の外部株主を尊重した経営を行うかどうかに懸念が残ります。また、子会社の上場はグループ企業の企業価値を外部に流出させる行為と見なされ、海外投資家からは評判が悪い制度です。
- 上場の意義を問われる企業: 上場企業の中には、業績が横ばいで株主還元にも消極的な企業が存在し、上場の意義が問われるケースもあります。これまでは明確な理由がなかったため、上場廃止を迫ることができませんでした。
上場維持基準の内容
2022年4月、東証は市場改革の一環として「上場維持基準」を公表しました。この基準は、上場企業が継続的に維持するための基準であり、基準に達しない企業には退場を促す措置が取られます。具体的には、以下の7つの基準が設けられています。
- 流通株式時価総額: プライム市場では100億円以上、スタンダード市場では10億円以上、グロース市場では5億円以上が求められます。この基準は、固定株主比率が50%の場合でも、時価総額が20億円以上であればクリアできます。
- 売買高: プライム市場では「1日平均売買代金が0.2億円以上」という基準があり、企業側がコントロールできないため、高いハードルとなっています。
- 純資産: 上場維持基準には「純資産がプラス」という条件があり、仕手株の多くは純資産がマイナスであるため、上場廃止の可能性が高まります。
上場廃止の流れ
上場維持基準に達しない企業は、各企業の事業年度の末日に判定が行われます。基準に達しない場合、企業は1年間の「改善期間」に入り、この期間内に基準に到達すれば、引き続き上場が維持されます。しかし、改善期間を経ても基準に達していなければ、以下の流れで上場廃止となります。
- 監理・整理銘柄指定: 改善期間後、基準に達しない場合は6か月間「監理・整理銘柄」に指定されます。
- 最終的な上場廃止: その6か月が経過しても基準に達していなければ、最終的に上場廃止となります。
今後の展望
上場維持基準の適用により、上場廃止が進むことで、グロース市場の回復が期待されます。近年の国内市場は大型株中心の展開となっており、グロース銘柄は低迷が続いています。上場維持基準の導入は、東証の新陳代謝を促進し、より健全な市場環境を作るための重要なステップとなるでしょう。
また、仮に東証で上場廃止となっても、上場基準が緩い名古屋証券取引所などの地方取引所で上場を続ける企業も出ると予想されています。このように、上場維持基準の導入は、東証の市場改革において重要な役割を果たすことが期待されています。今後の制度の行方とその影響に注目が集まります。

 |  |