日本の外食チェーン、サイゼリヤ、餃子の王将、くら寿司などは、中国市場に進出し、巨大な消費者層をターゲットにしてきました。しかし、成功例は限られており、多くの企業が苦戦を強いられています。
成功した企業の例
吉野家は1992年に中国市場に進出し、現在では北京を中心に500店舗以上を展開しています。サイゼリヤも2003年に上海で初店舗を開店し、全体で500店舗を超える成功を収めています。特にサイゼリヤは、2023年8月期に国内事業が赤字となったものの、アジア事業で84億円の利益を上げ、赤字を補填しました。
失敗した企業の例
一方で、餃子の王将は中国市場から撤退を余儀なくされ、くら寿司も2023年に進出したものの、現地のニーズをつかめず、3店舗を年内に閉店すると発表しました。くら寿司は当初、100店舗を展開する計画でしたが、実際には上海の3店舗にとどまり、2年間で11億円の損失を計上しました。
中国市場の特性
中国市場は人口が多いものの、実際に日本企業がターゲットにできる購買力を持つ層は限られています。日本人と同等の購買力を持つのは10人に1人程度であり、実質的には約1.4億人がターゲットとなります。このため、価格競争力が低く、現地企業との競争が厳しい状況です。
現地化の重要性
成功するためには、現地の嗜好に合わせたメニューの提供が不可欠です。スシローは「生ものが苦手」という中国人の嗜好に合わせ、加熱した商品を増やして現地化を進めています。また、味千ラーメンは中国市場で約600店舗を展開し、現地の味に適応したメニューを提供することで成功を収めています。
結論
日本の外食チェーンが中国市場で成功するためには、現地のニーズを理解し、適切な価格設定とメニューの現地化が求められます。中国市場は巨大ですが、競争が激しく、慎重な戦略が必要です。今後の動向に注目が集まります。
 |  | |
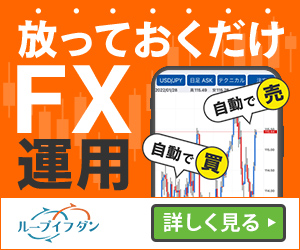 |  |

