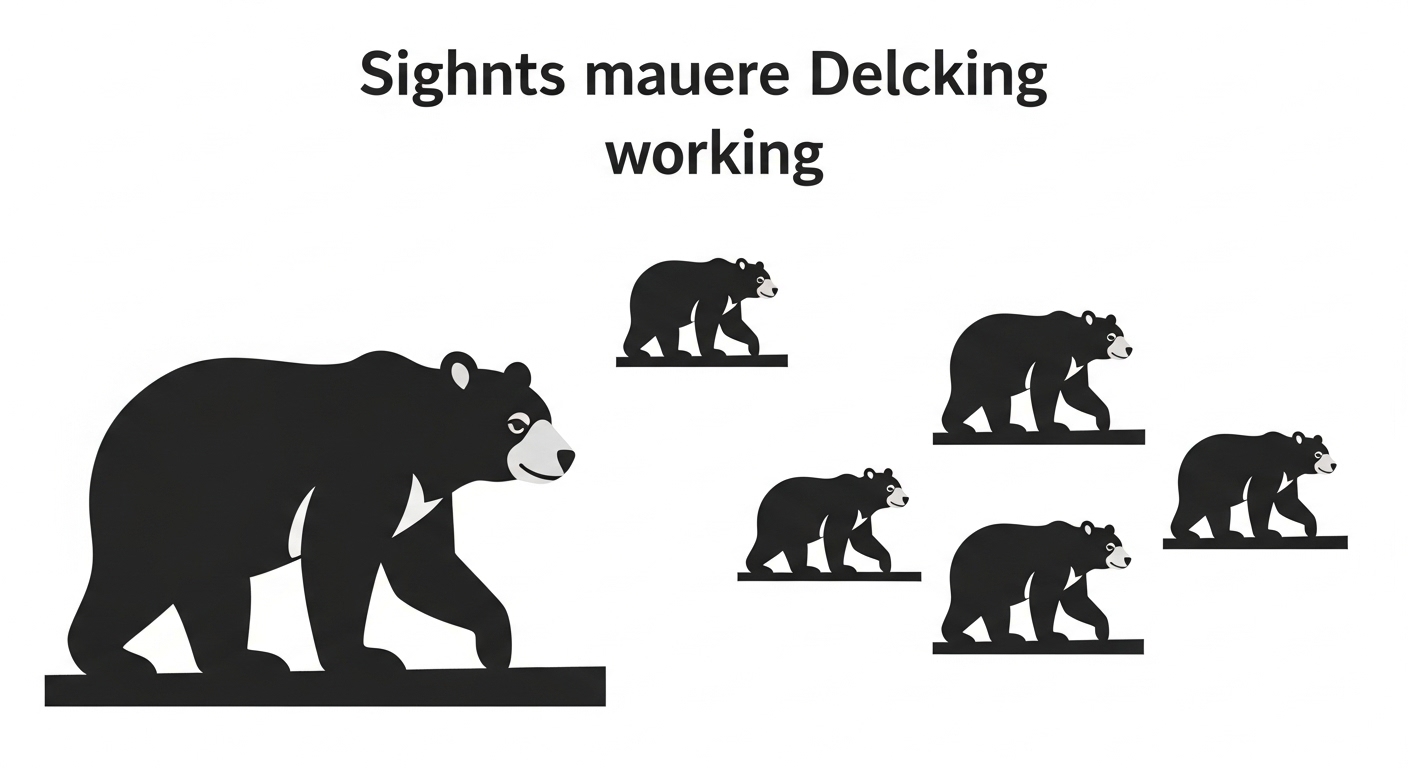長野県箕輪町で、2025年度のツキノワグマ目撃件数が昨年度の半分以下となる9件(10月24日時点)にとどまりました。
また、シカ用のわなに誤ってかかる「錯誤捕獲」も3頭で、昨年度の17頭から大幅に減少。
町は今年6月から導入した「ゾーニング」(熊の生息域と人の生活空間の区分)が大きな効果を上げたとみています。
▶️ 万が一の遭遇時に備える必携アイテムならクマ撃退スプレーがおすすめ!!
ゾーニングとは?人と熊の距離を保つ新たな共存策
「ゾーニング」とは、ツキノワグマが生息する山林と、人々の生活圏の間に緩衝地帯を設け、互いの領域を明確に区分する取り組みです。
箕輪町では、特にクマの目撃が多かった地区を中心に、やぶの刈り払い費用を補助するなど、地域ぐるみでの対策を進めてきました。
こうした動きは長野県内にも広がっており、県森林づくり推進課によると、現在、県内の10市町村がゾーニングを導入。上伊那地域では伊那市と箕輪町が実施しています。
白鳥政徳町長は「クマに市町村境は関係ない」と強調し、県全体での広域的な熊対策を進めるよう求めています。
なぜ熊の目撃が減ったのか?考えられる5つの理由
- ゾーニングによる生息域分離
熊の行動範囲と人の生活圏を分けることで、遭遇リスクを低減。 - 藪刈り補助制度の効果
クマが身を隠せる場所を減らし、住宅地への進入を防止。 - 誘引物(木の実・果実)除去の徹底
放置された果実がクマを引き寄せることを防ぐ。 - 農地保護対策の強化
リンゴ畑などに電気柵や防護ネットを設置。 - 住民・猟友会・行政の連携強化
地域ぐるみでの取り組みが実を結んだ形です。
減少=安全ではない、今後は広域的な連携が鍵に
ツキノワグマの目撃件数が減ったからといって、生息数そのものが減少したとは限りません。
特に秋は木の実や果実が少なくなる時期で、食料を求めて人里へ出てくるクマが再び増える可能性があります。
登山や農作業の際には、音を立てて存在を知らせる・クマ除けグッズを携帯するなど、日常的な備えが欠かせません。
一方で、箕輪町の取り組みは、地域主導による熊との共存を実現する好例として注目されています。
今後は県全体、さらには中部山岳地域を含めた広域的な情報共有とゾーニングの連携が求められます。
「クマと人が安全に共に生きる地域社会」を目指す上で、箕輪町の成功が新たなモデルケースとなる可能性が高いでしょう。
▶️ 万が一の遭遇時に備える必携アイテムならクマ撃退スプレーがおすすめ!!

 |  |