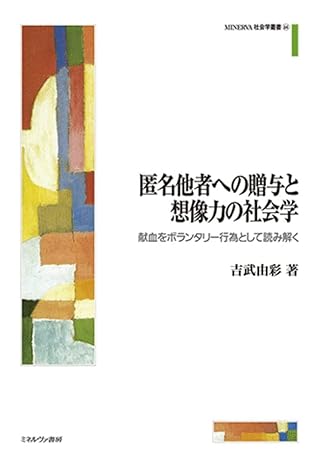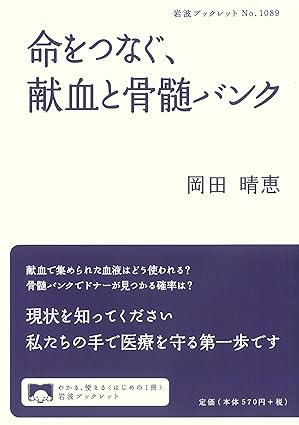日本赤十字社は2025年9月19日、記者会見を開き、5月以降に全国で発生した5件の不適切事案について公表し謝罪しました。事案はいずれも献血現場での安全管理ミスに起因しており、中でも最も深刻なものは使用済みの献血針を別の献血者に再使用するという、感染リスクを伴う重大なヒューマンエラーでした。血液事業は、輸血を必要とする患者にとって命綱とも言える重要な医療インフラです。こうしたミスは国民の信頼を揺るがしかねず、日本赤十字社は「国民の皆様の不安を払拭し、安全な献血体制を取り戻すために全力を尽くす」と述べ、再発防止策の徹底を約束しました。
北海道の移動献血会場で発生した針再使用のミス
最も注目されたのは、9月2日に北海道の移動献血会場で発生した事案です。現場では、直前に献血を受けた女性に使用した針を誤って廃棄せず、次に献血を受ける男性に再び使用してしまいました。スタッフは針を交換したと誤認しており、二重確認の手順が徹底されていなかったことが原因とされています。移動献血車では、限られたスペースと時間で多数の献血者に対応するため、作業が立て込みミスが起きやすい状況にあります。今回の事案は、そうした環境下でもミスを防げる業務フローの見直しや、器具管理のダブルチェック体制の必要性を改めて浮き彫りにしました。
健康被害はなし、しかし信頼低下と献血離れの懸念
日本赤十字社は、誤って針を再使用された男性に健康被害や感染症の兆候がないと報告しました。しかし、献血は国民の善意によって支えられている社会的活動であり、こうした事案は「自分も同じ目に遭うかもしれない」という不安を招きます。特に若年層の献血参加率は近年低下傾向にあり、血液確保が慢性的な課題となっている中での今回のニュースは、さらなる献血離れを引き起こす恐れがあります。輸血用血液が不足すれば、手術やがん治療、出産など医療現場に深刻な影響を及ぼしかねません。日本赤十字社は迅速な情報公開と安全性向上の取り組みを進めることで、国民の不安を払拭する必要があります。
日本赤十字社が発表した再発防止策と全国一斉点検
会見では、全国すべての献血会場および移動献血車で業務手順が正しく守られているかを点検する「一斉点検」を実施すると発表されました。さらに、針や器具の廃棄・交換の確認を二重化し、現場スタッフに対する再教育と定期研修を強化します。マニュアルの改訂も進め、針の廃棄記録をデジタル化するなど、ミスを未然に防ぐ仕組みの導入が検討されています。日本赤十字社は「形式的な点検に終わらせず、現場で実際に機能する安全対策を確立する」としており、今後は外部監査の導入も視野に入れているといいます。
過去の類似事例と海外の安全対策
献血現場での安全管理ミスは、国内外で過去にも発生しています。日本では2010年代にも、血液バッグの取り違えや、器具の交換忘れといった事案が報告されており、そのたびに手順の見直しが行われてきました。海外では米国赤十字社が2008年に針の再使用に関する不適切事案でFDA(米国食品医薬品局)から警告を受け、大規模な教育改革とチェック体制強化を行った事例があります。欧州でもダブルチェックの義務化やバーコードによる器具管理システムが導入され、再使用ミス防止に成功している国が多いです。今回の日本赤十字社の取り組みも、こうした海外事例を参考に、より高度な安全管理体制を構築する必要があります。
専門家が語る「信頼回復のカギ」
医療安全学の専門家である○○大学の△△教授は「今回の事案は単なる人為的ミスではなく、組織としての安全文化の問題が背景にある」と指摘します。教授によれば、単に手順を守るよう指導するだけでは再発防止には不十分で、現場が安全を最優先できるような環境づくりが必要だといいます。例えば、作業負荷を軽減する人員配置、心理的安全性を確保した報告制度、デジタル技術を活用したチェック機能の導入などが有効だとされます。「献血は国民の信頼があって初めて成り立つ。徹底した情報公開と現場改善が、信頼回復の第一歩になる」と教授は強調しています。
献血の安全性を取り戻すために求められること
今回の一連の事案は、献血という社会的インフラの脆弱性を改めて浮き彫りにしました。安全性を取り戻すためには、現場での手順徹底だけでなく、第三者による監査や外部評価を取り入れ、改善状況を定期的に公開することが求められます。国民が安心して献血に参加できるよう、透明性の高い情報発信と、失敗を許容し改善に活かす安全文化の醸成が不可欠です。献血者、医療機関、行政が協力し、持続可能な血液供給体制を築いていくことが今後の課題となるでしょう。す。

 |  |