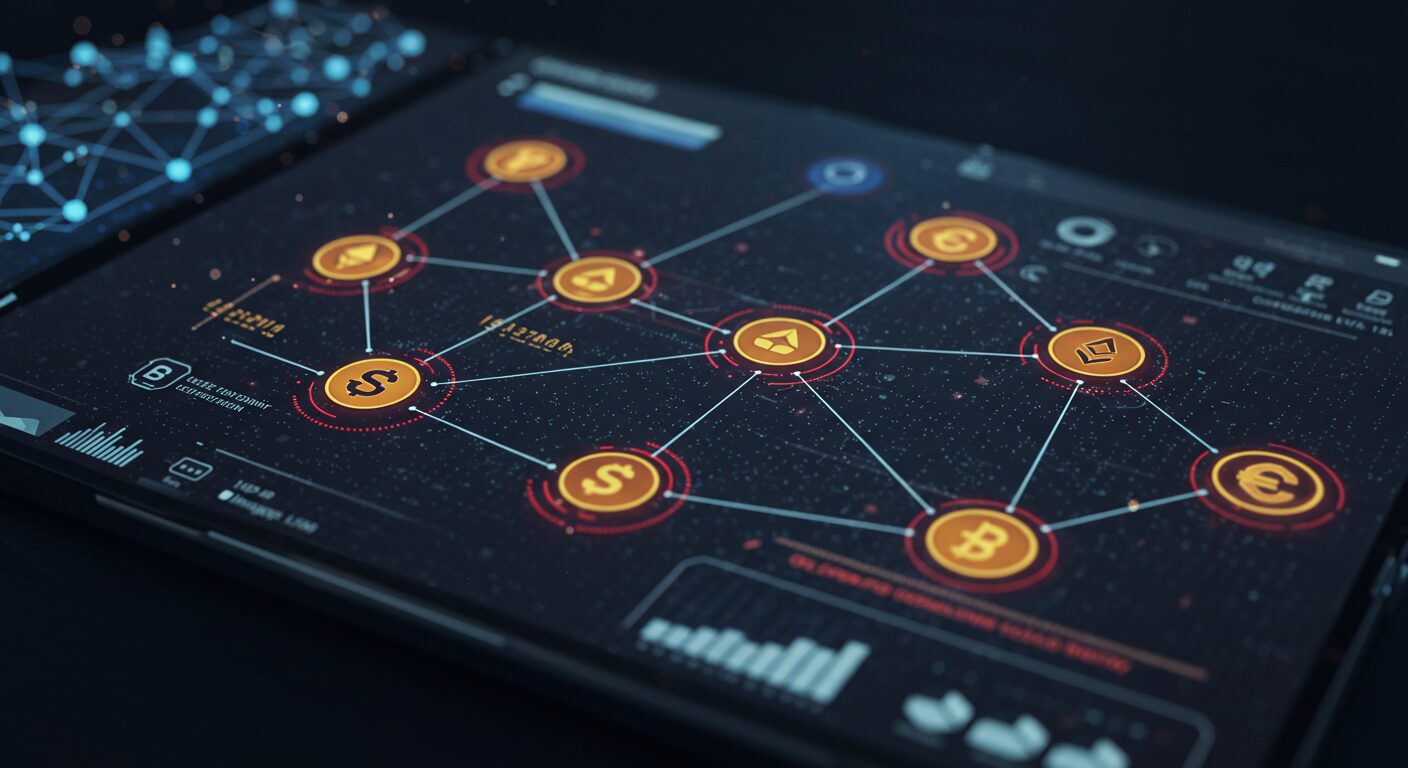ステーブルコインとは、価値が極端に上下しやすいビットコインやイーサリアムなどの暗号資産とは異なり、価格を一定に保つよう設計された資産のことです。一般的には「1枚=1米ドル」や「1枚=100円」といった形で、ドルや円などの法定通貨、または金などの資産に価値を連動させることで、利用者が安心して取引や送金に使えるように作られています。
暗号資産市場は非常に変動が激しいため、投資家や利用者が「価格の乱高下に影響されない資産」を必要とするケースは少なくありません。そこで登場したのがステーブルコインであり、こうしたニーズに応える形で急速に普及してきました。たとえば「テザー(USDT)」や「USDコイン(USDC)」といった代表的な銘柄は、世界中の暗号資産取引所や分散型金融(DeFi)の世界で幅広く利用されています。
さらに、ステーブルコインは単なる価格安定資産にとどまらず、ブロックチェーン技術を活用した新しい金融サービスの基盤としても重要です。NFT取引の決済手段や国際送金の効率化、さらには新興国におけるインフレ対策の手段としても使われており、現実世界とデジタル経済をつなぐ存在として注目されています。
⬇️初心者におすすめの参考書籍⬇️
ステーブルコインが注目される理由
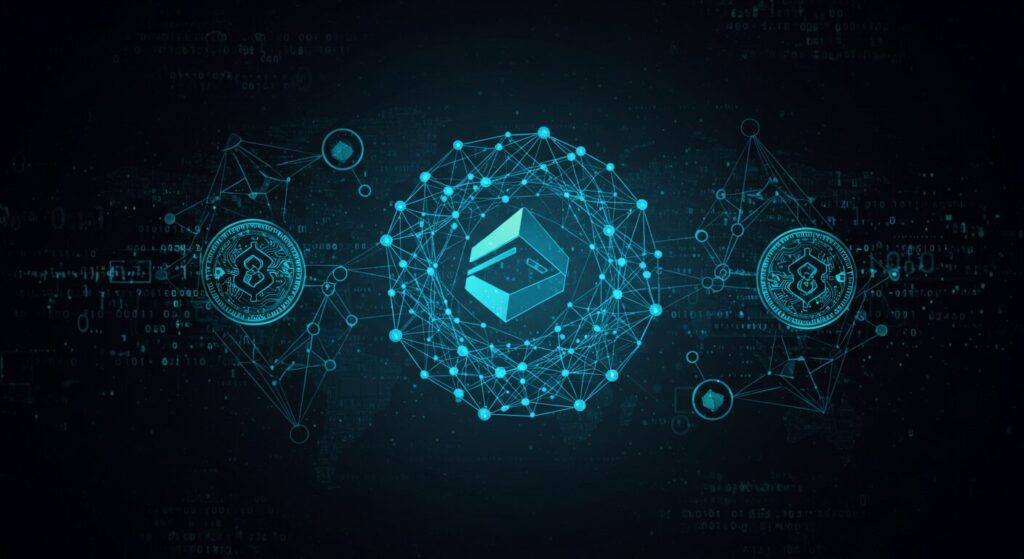
ステーブルコインがここまで注目される最大の理由は「価格の安定性」です。ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産は数時間のうちに大きく値動きするため、長期的な投資対象としては魅力があっても、日常生活の中で商品やサービスの支払いに使うのは不向きです。一方、ステーブルコインであれば法定通貨とほぼ同等の価値を維持できるため、日々の取引に安心して利用することができます。
また、国際送金における利便性も注目されています。従来の銀行を使った海外送金は、数日かかるうえに数千円単位の手数料が発生することが多いものでした。しかし、ステーブルコインを利用すれば数分以内で取引が完了し、手数料も数十円から数百円程度に抑えられます。こうした特長は、金融インフラが十分に整備されていない新興国において特に有効です。
さらに、NFTやDeFiといった新しいブロックチェーン経済圏においても、ステーブルコインは欠かせない存在です。NFTの取引では安定した通貨で決済を行うことが望ましく、DeFiではレンディングや利息運用の基盤として広く利用されています。加えて、アルゼンチンやトルコなどインフレ率の高い国々では、自国通貨よりも安定したステーブルコインを日常の支払いに使うケースも増えています。このように、価格の安定性だけでなく、世界的な金融課題を解決する力を持っている点が、ステーブルコインが注目される理由といえるでしょう。
⬇️さらに学びたい人向け⬇️
ステーブルコインの種類① 法定通貨担保型

法定通貨担保型のステーブルコインは、もっとも代表的で広く利用されているモデルです。これは銀行口座や信託口座に実際のドルや円などを預け、その裏付けをもとにステーブルコインが発行される仕組みです。たとえば、1ドルを銀行に預けると1USDTや1USDCが発行され、利用者は「1コイン=1ドル」という安心感を持って利用することができます。
このモデルは非常にわかりやすく、初心者にとっても理解しやすい仕組みであることから、世界中の取引所で標準的に採用されています。ただし注意すべき点もあります。それは「本当に預けられた資産が十分に存在するのか」という透明性の問題です。過去には一部のステーブルコインに対して、裏付け資産の不足や会計の不透明さが指摘されたこともありました。そのため、法定通貨担保型のステーブルコインを利用する際には、発行元の信頼性や監査体制をしっかり確認することが重要です。
ステーブルコインの種類② 暗号資産担保型

暗号資産担保型のステーブルコインは、イーサリアムやビットコインといった暗号資産を担保に入れて発行される仕組みです。代表的な例としては、分散型プロジェクトMakerDAOが提供する「DAI」があります。このモデルの特徴は、法定通貨や中央機関に依存せず、完全にブロックチェーン上で担保と発行が管理される点です。
ただし、暗号資産は価格変動が大きいため、担保として預ける際には「過剰担保」が必要になります。たとえば、100ドル分のステーブルコインを発行するには、150ドル以上のイーサリアムを担保として預けなければならない、といった仕組みです。これにより、担保資産が多少値下がりしてもステーブルコインの価値が維持されるように工夫されています。しかし、価格が大幅に下落した場合には強制的に担保が清算されるリスクがあるため、利用者は注意が必要です。
それでも、暗号資産担保型は透明性が高く、スマートコントラクトによって自動的に運営されるため「中央集権リスクがない」という強みを持っています。この特長から、DeFiの分野では特に重宝されています。
ステーブルコインの種類③ 無担保(アルゴリズム型)

無担保型、いわゆるアルゴリズム型ステーブルコインは、資産を裏付けにせず、プログラムによって供給量を調整して価格を維持する仕組みです。需要が高まれば自動的に発行量を増やし、需要が減れば供給を減らすことで「価値の安定」を保とうとします。
この仕組みは革新的であり、理論上は資産を保有しなくても安定性を維持できるという魅力があります。しかし現実には、アルゴリズムだけで価格を完全にコントロールするのは難しいことが証明されています。代表的な例として「TerraUSD(UST)」が挙げられます。2022年にUSTは大規模な暴落を起こし、わずか数日でほぼ無価値となりました。この事件は「アルゴリズム型ステーブルコインの信頼性」への大きな疑念を生むこととなり、暗号資産市場全体にも大きな衝撃を与えました。
初心者にとってはリスクが高いため、まずは法定通貨担保型や暗号資産担保型を理解したうえで、仕組みを勉強する程度にとどめておくのがおすすめです。
ステーブルコインのメリットとデメリット

ステーブルコインの最大のメリットは「価格の安定性」です。暗号資産の世界はボラティリティが大きく、投資の観点では魅力的である一方、日常利用には不安が伴います。ステーブルコインであれば、ほぼ法定通貨と同じ感覚で取引ができるため、決済手段や送金手段として安心して利用できます。また、国際送金のコスト削減や、NFT・DeFiにおける決済手段としても重要な役割を果たしています。
しかしデメリットも存在します。法定通貨担保型では発行元や銀行の信頼性に依存してしまうリスクがあり、透明性が不足するとユーザーに不安を与えます。暗号資産担保型は分散性が強みである反面、担保資産の急落時には清算リスクがあります。そしてアルゴリズム型は、供給調整が機能しない場合には短期間で大きな損失を被る可能性があるのです。
つまり、ステーブルコインを活用するには「どのタイプを使うのか」を見極め、それぞれのリスクを理解することが欠かせません。
ステーブルコインの今後の展望
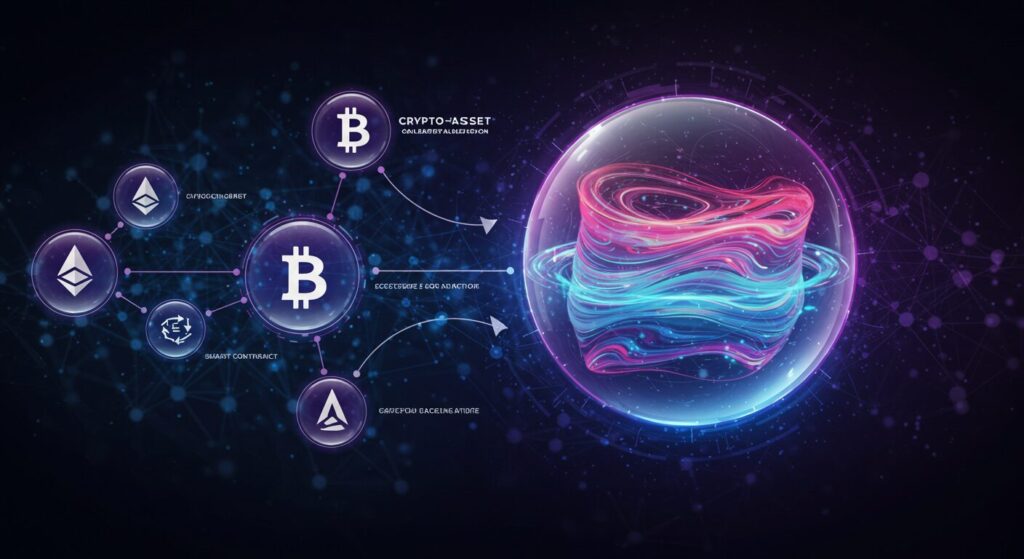
ステーブルコインは今後、国際金融や日常決済においてますます重要な役割を果たすと予想されています。特に注目されているのは、各国の中央銀行が研究・開発を進める「CBDC(中央銀行デジタル通貨)」との関係です。CBDCは国家が直接発行するデジタル通貨であり、ステーブルコインと競合する可能性もあれば、共存して金融システムを補完し合う未来も考えられます。
また、規制の整備が進めば信頼性が高まり、金融機関や一般消費者にも広く普及する可能性があります。すでに米国や欧州ではステーブルコイン規制に向けた議論が本格化しており、日本でも金融庁がガイドラインを発表しています。これにより、利用者が安心して使える環境が整えば、投資や資産保護だけでなく、コンビニやオンラインショップでの支払いなど日常生活でも当たり前に使われる未来がやってくるかもしれません。
ステーブルコインは「暗号資産の世界を支える安定資産」として、今後もその重要性を高めていくと考えられます。

 |  |