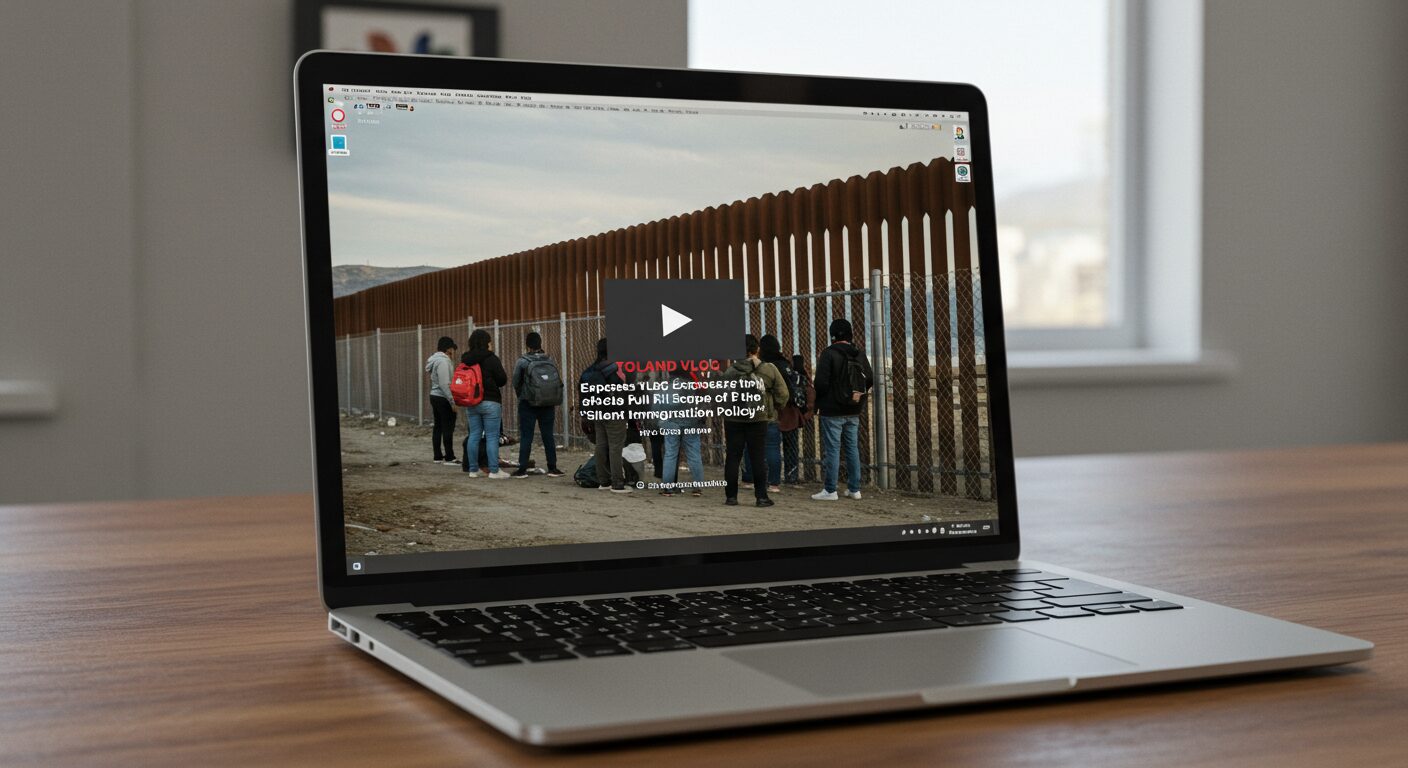「日本は移民政策を取らない」――。
この言葉を、何度政府の口から聞かされてきただろうか。
しかし、実際に進行している制度改革の中身を丁寧に追えば、その言葉が“政治的な方便”に過ぎないことが浮かび上がる。
YouTubeチャンネル TOLAND VLOG は、2025年秋に公開した動画でこの問題を鋭く告発した。
同チャンネルは、「政府が『移民政策』という言葉を避けながら、実質的に移民受け入れを進めている」と指摘。
制度、データ、そして社会現場の変化を挙げながら、日本がすでに「移民国家への道」を歩み始めていると警鐘を鳴らした。
目次
■ 第1章 “アフリカ・ホームタウン構想”の炎上が示した違和感
2025年8月、国際協力機構(JICA)が打ち出した「アフリカ4カ国と日本の4都市を結ぶホームタウン構想」。
この発表自体は、国際交流を促進する文化事業として位置づけられていた。
だが、その翌日、ナイジェリア政府の公式サイトが「日本がナイジェリア人向けに特別ビザを発行する」と投稿。
瞬く間にSNS上で「日本がアフリカ移民受け入れを開始した」「政府が国民に黙って移民政策を進めている」と炎上が広がった。
外務省とJICAは即座に否定。投稿は削除されたが、TOLAND VLOGはこの一件を単なる誤報として終わらせなかった。
動画内では「この騒動は、“本当の移民拡大政策”から世論の目を逸らすための偶然のカモフラージュとして機能した」と分析。
確かに、メディアはこの話題を“誤報騒動”として処理し、
その裏で同時期に進行していた「特定技能2号の対象拡大」「技能実習制度の廃止決定」にはほとんど触れなかった。
「あのニュースで国民は“移民政策なんてまだ先の話”と安心した。
だが現実には、すでに制度が完成しつつある」(TOLAND VLOGより)
■ 第2章 「移民政策を取らない」という言葉のトリック
TOLAND VLOGが最も強調するのは、「移民」という言葉の使われ方だ。
日本政府は長年、「移民政策は取らない」という立場を堅持してきた。
しかし、その根拠は“移民の定義を狭く設定している”ことにある。
国際機関(OECDや国連)では、1年以上外国に居住・労働する人を「移民」と定義する。
だが日本政府は、「技能実習生」「留学生」「特定技能労働者」などをあくまで“期間限定滞在者”として扱い、
移民統計から除外している。
その結果、2019年に日本が新規に受け入れた外国人は**約49万人(OECD統計で世界第4位)**でありながら、
政府の発表上は「移民国家ではない」という説明が可能になっている。
「“移民”を“外国人”という別の箱に入れ替えただけ。
言葉の操作によって政策の実態を隠している」(TOLAND VLOGより)
動画では、「日本が移民を受け入れていない」という信念そのものが、すでに“情報のフレーム操作”によって作られた幻想だと断じている。
■ 第3章 2018年から始まった“静かな移民国家化”
2018年の入管法改正が、すべての転換点だった。
ここで新設されたのが「特定技能制度」である。
- 特定技能1号:在留期間5年、更新可、転職制限あり
- 特定技能2号:在留期間の制限なし、家族帯同可、永住申請可能
当初は建設や造船など“人手不足が深刻な分野”に限定されていたが、
2023~2024年には運送・農業・介護・外食・宿泊業などにまで拡大。
結果として、日本の労働市場の大半が対象となった。
つまり、名目上は「技能労働者」でありながら、
実態は“長期定住を前提とする外国人”の受け入れ政策になっている。
さらに、これと並行して2024年に発表された「外国人技能実習制度の廃止」。
その代わりに、2027年から導入される「育成就労制度」では、
転職の自由や長期在留を認めるなど、定住をより容易にする仕組みが盛り込まれている。
「“技術を学んで帰る”制度から、“定住して働く”制度へ。
名前を変えただけで、実質的な移民制度に進化した」(TOLAND VLOGより)
■ 第4章 “数字が語る現実”――外国人労働者はすでに200万人超
厚生労働省によると、2025年時点で日本で働く外国人労働者は約206万人。
これは10年前の2倍以上の数字であり、人口比にして約3%に達する。
さらに、東京・名古屋・大阪の一部地域では外国人居住者が人口の10~15%を占めるようになっており、
「地方のコンビニや工場が外国人で成り立っている」という現実が広がっている。
TOLAND VLOGは、これを「政策による“静かな民族構造の変化”」と表現。
「誰も気づかないうちに社会の構成が変わっている」と警告を発した。
■ 第5章 教育・地域社会で起き始めた“文化摩擦”
日本語を母語としない子どもの数は、文部科学省の統計で6万人を突破。
地方自治体によっては、外国ルーツの児童が教室の3分の1を占める学校もある。
教員の多くが言語支援の専門知識を持たない中、
教育現場は“多文化共生”を名目に制度的支援の拡充を迫られている。
また、地域コミュニティでは、文化・宗教・生活習慣の違いによる摩擦も報告されている。
ゴミ出しや防災訓練、地域行事の参加率の低下――。
「多様性」を掲げる一方で、現実には新たな分断が生まれ始めている。
「制度だけが先に走り、社会の準備が追いついていない。
これが欧州の失敗と同じ道になる可能性がある」(TOLAND VLOGより)
■ 第6章 欧州の失敗、カナダの成功――日本はどちらへ向かうのか
TOLAND VLOGでは、海外の移民政策の比較にも時間を割いた。
スウェーデンやドイツでは、無制限な移民受け入れによって治安悪化や社会分断が進行。
一方で、カナダは厳格なスキル審査と語学教育支援によって比較的安定した移民政策を実現している。
「日本は“安価な労働力確保”に偏りすぎており、
人材の質ではなく“数”を基準に受け入れている」(TOLAND VLOGより)
日本の現行制度は、経済的即戦力を優先するあまり、
社会統合・文化教育の仕組みを軽視している点が最大のリスクだ。
■ 第7章 官僚・企業・メディアの“癒着構造”
動画ではさらに、制度拡大の背後にある「利権構造」にも踏み込んだ。
外国人受け入れに関連する研修・監理団体、派遣企業、行政委託事業などに巨大な利権が生まれており、
政治家OBや官僚が天下る構造が形成されているという。
また、メディアもスポンサー企業との関係上、移民受け入れをポジティブに報道する傾向が強い。
これにより、「移民政策反対」という声が“差別的言動”として封じられる状況が生まれている。
■ 第8章 「議論なき政策」が生む社会の歪み
日本では「移民政策」という言葉自体がタブー視されてきた。
その結果、制度は拡大しているのに、国民的議論はほとんど行われていない。
この“沈黙”が最大の問題だとTOLAND VLOGは警告する。
国民が無関心のまま制度が完成すれば、それは民主主義の空洞化につながる。
「国民が知らないうちに国の構造が変わっていく。
それは独裁でも陰謀でもなく、“無関心による崩壊”だ」(TOLAND VLOGより)
■ 結論:日本はどこへ向かうのか
いま日本社会は、明確な選択を迫られている。
・このまま「実質的な移民国家」として歩むのか
・それとも、統合政策を伴う新しい社会モデルを作るのか
TOLAND VLOGの動画は、その問いを国民一人ひとりに突きつける内容だった。
「移民を受け入れるかどうか」ではなく、
「移民国家としてどう生きるのか」を問う時代に、日本はすでに入っているのかもしれない。

 |  |