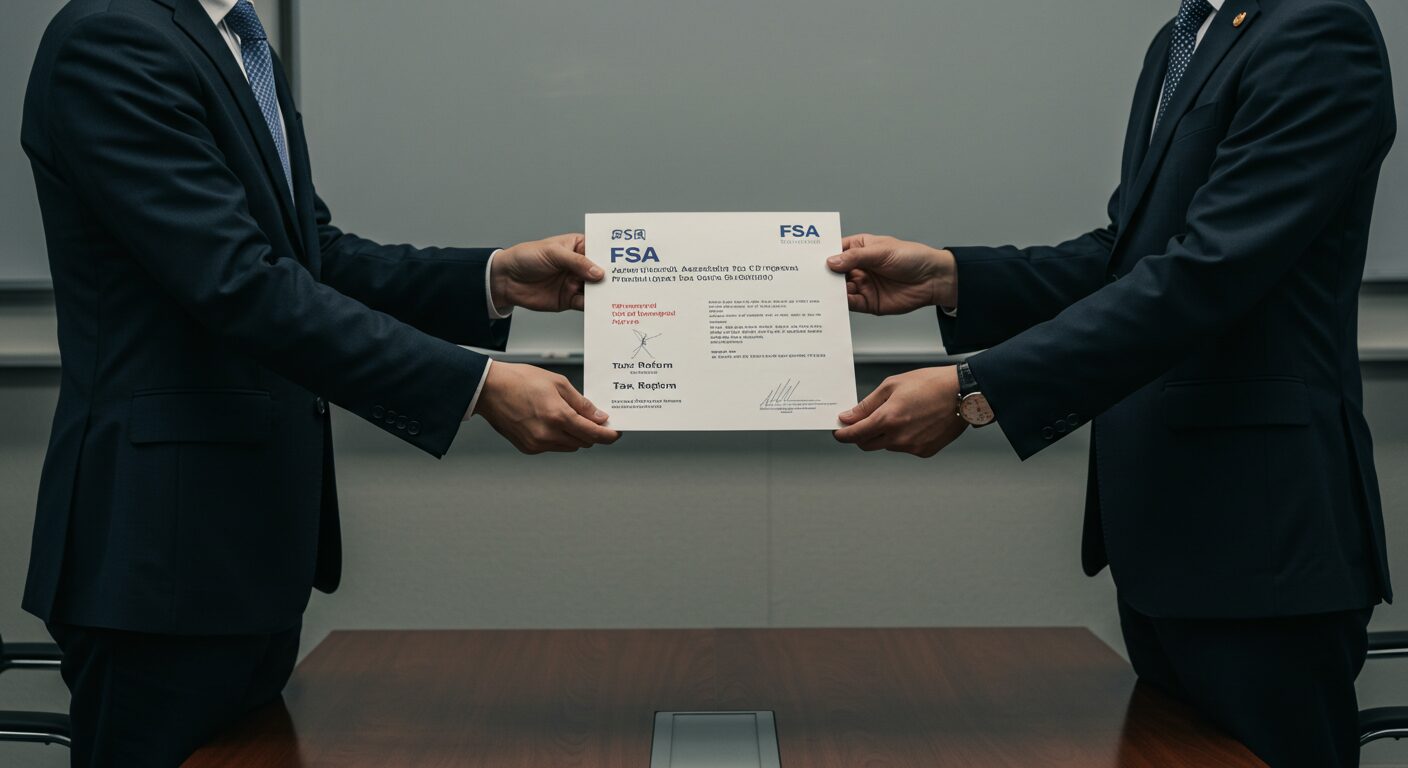日本ブロックチェーン協会(JBA)は2023年7月18日、2026年度の「暗号資産に関する税制改正要望」を金融庁に提出し、都内で記者会見を開きました。登壇したのは、JBA代表理事で暗号資産取引所ビットフライヤーのCEOを務める加納裕三氏と、JBA税制分科会長でDeFiやNFT領域のプラットフォーム開発を手がけるNewLO取締役CFOの岩﨑宏太氏です。
要望の主な内容
JBAが提案した要望の柱は以下の通りです:
- 分離課税・損失の繰越控除の導入
暗号資産の売却益に対する課税を、現行の最大55%の総合課税から、株式と同じ20.315%の分離課税に変更することを求めています。また、損失が出た場合には、3年間の繰越控除を可能とすることも要望しています。 - 相続時の取扱いの見直し
現行制度では、相続時の価格と売却時の取得価格が異なるため、実際には利益が出ていないのに所得税が発生するケースがあるため、相続税の取り扱いを見直す必要があります。 - 暗号資産同士の交換時の課税を繰り延べ
現行制度では暗号資産同士の交換時に課税されるため、取引が煩雑になっています。JBAは、法定通貨に変えた時点で課税することを求めています。 - 暗号資産を寄附した際の非課税措置の適用
寄附時に課税される現行制度を見直し、寄附を促進するための非課税措置を求めています。 - 法人による暗号資産保有への期末時価課税見直しの継続検討
法人が保有する暗号資産に対する課税の見直しを求めています。
背景と懸念
加納氏は、国内市場の拡大と諸外国と比べて「著しく重い税負担」を指摘し、特に米国ではビットコイン現物ETFの運用残高が1400億ドルを超え、資産形成手段としての地位が確立しつつあると述べました。日本でも暗号資産の口座数が1200万を超え、投資経験者の7.3%が暗号資産を保有していることから、一般投資家の資産形成手段としての暗号資産の位置づけが変わりつつあると強調しました。
また、金融商品取引法の下で暗号資産を「金融商品」として位置づける議論が進む中、現物取引とETF取引で課税方式が異なる「ねじれ」が生じる可能性があることも懸念されています。これにより、資金がETFに流れ、現物取引の流動性が低下し、国内のWeb3産業の成長を阻害する恐れがあります。
今後の展望
加納氏は、税制の差を意識して投資先を選ぶ現状を踏まえ、暗号資産への分離課税の導入やETFの承認が健全な投資市場の形成につながるとの見方を示しました。JBAは、これらの要望が実現することで、暗号資産市場の健全な拡大が期待できるとしています。

 |  |