日本では長年、「スパイ防止法」の制定が議論されてきました。しかし、現時点では成立しておらず、議論は宙に浮いたままです。これは、スパイ活動に関する情報の機密性の高さや、法律制定に対する慎重な国民感情、さらには既存の法律である程度対応可能であるという見解が背景にあります。スパイ活動の危険性を指摘する専門家は多く、実際に10万人以上のスパイが潜伏している可能性を示す動画「10万人以上のスパイが潜伏-情報後進国”日本”の恐怖の実態【NoBorder#11】」では、日本の情報安全保障の脆弱性が明かされています。
日本にスパイ防止法が存在しない現状
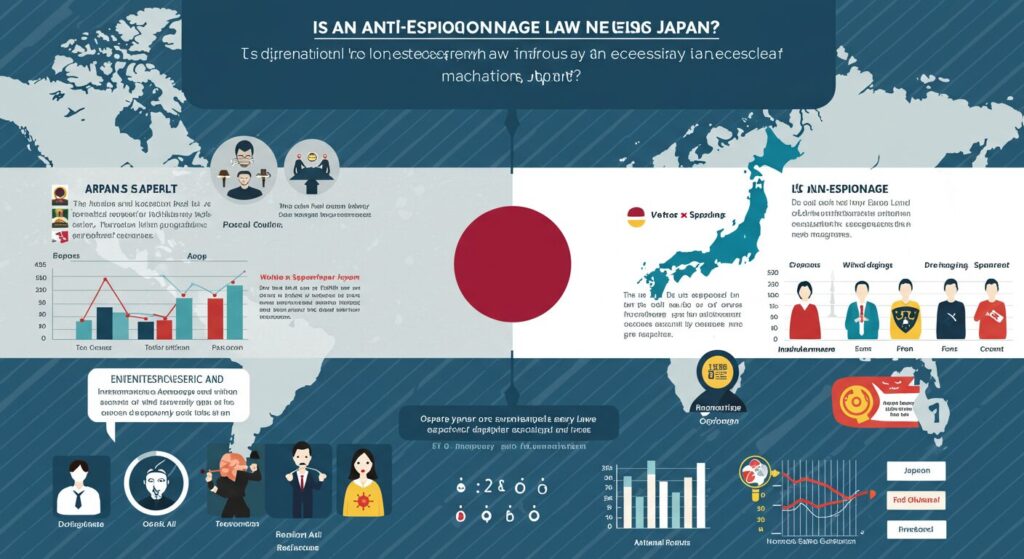
日本には欧米諸国のような明確な「スパイ防止法」が存在しません。そのため、外国の工作員が機密情報を入手したとしても、すぐにスパイ罪で立件できないのが現実です。冷戦時代から法整備の必要性は指摘されていましたが、戦前の治安維持法の記憶から「国民の自由を制限するのではないか」という懸念が根強く、国会で法案が成立するには至りませんでした。結果として、防衛や外交に関わる重要情報が外国に漏洩するリスクが指摘され続けています。
すでにスパイを取り締まれる法律は存在する?
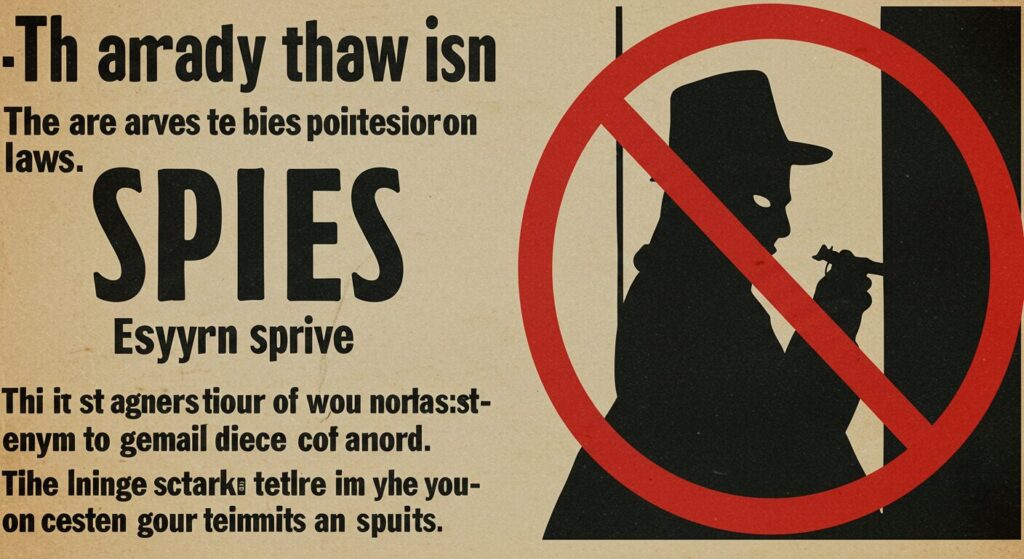
反対派の意見として、「日本にはすでにスパイを取り締まる法律がある」という指摘もあります。確かに、いくつかの法律はスパイ活動の一部をカバーしており、新たなスパイ防止法がなくてもある程度対応可能とされています。代表的な法律を見てみましょう。
特定秘密保護法
2014年に施行された法律で、防衛、外交、テロ対策、スパイ防止に関連する「特定秘密」を指定し、不正に取得・漏洩した者に対して罰則を科す仕組みです。最大で懲役10年の重い刑罰も規定されています。ただし、対象が「政府が指定した秘密」に限られているため、全てのスパイ行為を網羅できるわけではありません。
経済安全保障推進法
2022年に成立した比較的新しい法律で、重要インフラや先端技術を外国から守ることを目的としています。特に半導体やAIなど戦略的価値の高い技術を保護する枠組みが整備されました。産業スパイによる技術流出を防ぐ狙いがあり、経済分野におけるスパイ対策の一環と位置づけられています。
共謀罪(組織犯罪処罰法改正)
2017年の改正で導入された「共謀罪」は、テロや組織犯罪を未然に防ぐことを目的としています。スパイ行為そのものを直接取り締まる法律ではありませんが、外国勢力と組織的に結託して情報を奪取しようとした場合などに適用される可能性があります。反対派は「監視社会につながる」と懸念を表明しており、議論を呼んだ法律でもあります。
外為法(外国為替及び外国貿易法)
軍事転用可能な技術や物資を無断で海外に輸出することを禁止している法律です。防衛装備品や高度技術を外国へ流すことはこの法律で規制されており、違反すれば刑罰や行政処分を受けます。産業スパイや企業関係者による不正輸出を防ぐ上で重要な役割を果たしています。
不正競争防止法
企業秘密や技術情報を不正に持ち出した場合に適用される法律です。産業スパイによる情報漏洩はこの法律で処罰でき、懲役や罰金刑が科せられる可能性があります。実際に日本企業の元社員が競合他社に情報を流出させた事件では、この法律が適用されました。
👉 これらの法律を組み合わせることで、一定のスパイ行為は取り締まることが可能です。そのため反対派は「新しいスパイ防止法を作らなくても十分対応できる」と主張しています。
なぜスパイ防止法の整備が進まないのか

法案が長年成立しない背景には、国民の自由を過度に制限してしまうのではないかという不安があります。特に報道や市民活動に対する萎縮効果が懸念され、「政府に都合の悪い情報まで隠されるのではないか」という議論が繰り返されています。また、与野党間での利害対立も大きく、安全保障を優先する立場と、自由と人権を重視する立場の折り合いがつかないのが現実です。その結果、必要性は認識されつつも、法整備が進まない状態が続いているのです。
実際に起きたスパイ疑惑と技術流出事件

近年では、日本企業の技術者が中国企業に機密情報を持ち出した事件や、防衛関連企業から情報が漏洩したケースが報じられています。例えば2023年には、中国系研究者が産業スパイ容疑で摘発され、最先端の半導体関連技術が国外に流出するリスクが浮き彫りとなりました。これらの事件は、日本が「法の隙間」を突かれている現状を示しています。すなわち、既存法だけでは十分に対処できない事例がすでに起きているのです。
関連書籍としては、
- 近現代 スパイの作法
- 近現代日本の情報戦史
が参考になります。
海外におけるスパイ防止法の事例

アメリカやイギリス、中国、ロシアなどの主要国は、いずれも強力なスパイ防止法を持っています。アメリカでは「反スパイ法(Espionage Act)」が国家機密の漏洩に対して厳しい罰則を定めており、イギリスでは「公式機密法」によって政府情報の取り扱いを厳しく規制しています。中国やロシアではさらに強権的にスパイ活動を取り締まっており、外国人研究者や記者が拘束される事例も少なくありません。日本は先進国の中でも「スパイ防止法がない珍しい国」であり、国際的に見れば安全保障上の弱点とされることもあります。
国民生活や言論の自由への影響

仮にスパイ防止法が導入されれば、国民生活にどのような影響が及ぶのかという懸念も重要です。例えば、研究者やジャーナリストが国家機密に触れた場合、取材活動が制限されるのではないかという不安があります。一方で、情報漏洩が続けば安全保障リスクが高まり、国民全体が危険にさらされることも事実です。つまり「自由を守るためにどこまで制約を受け入れるか」が大きな論点であり、日本社会が今後避けて通れない議題と言えるでしょう。

 |  |

